最近、食料品から日用品、ガソリンや授業料まで、何でもかんでも全て値上げになっています。
この値上げはいつまで続くのか?先が見えません。
ですので、これからは出来る限り節約をしながら、暮らしていくしかありません。
原油価格や人件費等々が上がっていることから、電気代も上がらないはずもなく、電気料金はじわじわと上がってきています。
 ささ
ささ数年前までは、太陽光システムで電気を自家消費しながら売電していたので、電気代はあまり気にしなったのですが、卒FITで買取価格が下がってからは、じわじわと電気代が家計に効いてきています。
とはいえ、折角、毎日無料で発電してくれている「太陽光パネル」。少しでも生活費の足しに出来るように活用していく方法をご紹介していきたいと思います。
太陽光パネルとパワコンの寿命はどれくらい?


太陽光パネルとパワコンは、それぞれ異なる寿命を持っています!
実際にそれぞれの寿命がどれくらいなのか、そしてその寿命を延ばすためにはどうすれば良いのか?それ以外どんな選択肢があるのか?を書いていきたいと思います。
- 太陽光パネルの寿命は一般的に20~30年
- パワコンの寿命は10~15年程度
- 寿命を延ばすために必要なメンテナンス
太陽光パネルの寿命は一般的に20~30年
太陽光パネルの寿命は一般的に20年から30年程度と言われています。
但し、パネル自体は非常に耐久性が高いですが、時間とともに発電効率が徐々に低下します。太陽光パネルは、長年にわたり紫外線や気象条件にさらされるため、少しずつ劣化が進行するためです。
しかし、最新のパネルは性能が向上しており、劣化が遅く、一般的に20年を過ぎてもある程度の発電量を維持することができるケースも多くあります。



私の自宅も、パネルの使用年数は12年くらい経ちますが、発電量は導入当初から、ほぼ落ちずに使用出来ています。
パワコンの寿命は10~15年程度
パワコン(パワーコンディショナー)の寿命は、一般的に10年から15年程度とされています。
パワコンは発電した直流電流を交流電流に変換する重要な役割を果たしており、その耐久性は太陽光パネルに比べて短いです。
パワコンは非常に高温になることがあり、その熱負荷が寿命を縮める原因として考えられます。
その為、15年を過ぎると交換を考えるべき時期とされています。実際、パワコンの故障率は設置から10年を超えたあたりから増加すると言われています。
寿命を延ばすために必要なメンテナンス
太陽光パネルとパワコンの寿命を延ばすためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
パネルの汚れを定期的に掃除し、パワコンは温度管理や点検を行うことで、寿命を長く保つことができます。太陽光パネルが汚れていると発電効率が低下し、パワコンが過熱すると故障を引き起こす可能性が高くなるためです。



とはいえ、太陽光パネルは家の屋根に取り付け、パワコンの設置場所も高所なので、実際はメンテナンスは行っていないケースが多いのではと思います。私の自宅も10年間ノーメンテナンスで使用していました!!
太陽光パネル・パワコン“寿命=終わり”じゃない!システム寿命後も使い続ける
太陽光パネル・パワコンが寿命を迎えた後、太陽光システムは「もう使えない」と思っている方も多いかもしれません。しかし、寿命が近づいても、まだ使い続ける事も可能です。
この記事では、寿命を迎えた後でも使い続けるための方法を記載していきたいと思いますので、最後まで読んでください。
- 寿命後が近くなっても使い続けられる理由
- 最終的にはパワコンの交換が必要
寿命が近くなっても使い続けられる理由
太陽光システムを長く使用するには、パワコンのメンテナンスが重要
太陽光パネルは、寿命を迎えても完全に機能しなくなるわけではありません。実際、多くの太陽光発電システムは寿命を迎えた後でも、一定の発電能力を維持しているケースがあります。
太陽光パネルは劣化が進んでも、発電効率は完全にゼロにはならず、時間をかけて少しずつ低下していくためです。
但し、パワコン(パワーコンディショナー)は、故障が発生すると、せっかく太陽光パネルで発電した電力を利用する事ができなくなってしまいます。太陽光システムを使い続ける為いは、パワコンの変化・異変を見つけて早期に修理を行うことで、システム自体の寿命を延ばすことが可能です。
最終的にはパワコンの交換が必要
太陽光パネルはもともと寿命が非常に長く、また、完全に機能しなくなる訳ではなく、長い年数をかけて徐々に性能が低下していくという性質があります。その為、パネルの寿命も20年~30年と非常に長くなっている理由です。
対して、パワコンは、寿命が太陽光パネル程長くはなく、電子部品で構成されている為、突然の故障で使えなくなる事があります。
パワコンに故障が発生した場合は、新品への交換が必要です。
但し、パワコン交換のタイミングで、太陽光パネルはまだまだ元気です。なので、まだまだ発電して貰いたいと思うのが普通です。
しかし、その、タイミングでパワコンの製品の保証が残っている事はほぼなく、別途新しいパワコンの購入と設置工事の金額がかかってしまうことになります。
どうせパワコンを替えるなら、壊れる前にパワコンを含めた「蓄電池」を設置してしまうのも、一つの方法です。



我が家も、太陽光システムが十年を過ぎて、パワコンも怪しくなってきていて・・売電の買取価格も下がったので、良いタイミングと思い、「シャープ蓄電池」を導入しました。
我が家の蓄電池設置の「購入」~「効果」までを記事にしています。是非ご覧いただければと思います。
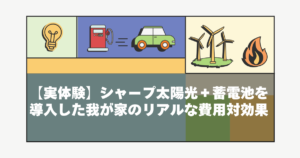
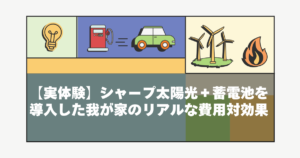
蓄電池を設置することで得られる3つの大きなメリット


蓄電池は、太陽光発電の効率を最大化し、電気代の節約にもつながります。ここでは、蓄電池を設置することによって得られる大きなメリットを3つ紹介します。
- 電気代の大幅な削減
- 災害時の電源確保
- 太陽光発電システムの効率最大化
メリット1:電気代の大幅な削減
蓄電池を設置することで電気代を大幅に削減できます。
太陽光パネルで発電した電力を蓄電池にためておけば、夜間や曇りの日でも自宅で使用できるため、電力会社から購入する電気の量を減らせます。
昼間に発電された電力を蓄電池に保存し、必要なときに使うことで、電力の無駄遣いを減らすことができるからです。特に、昼間に余った電力をそのまま売電するのではなく、自家消費することが可能になります。



蓄電池の設置で電気代の削減はもちろんですが、自宅の発電・蓄電・消費状況がモニター出来るようになりますので、節約の意識が強くなることでさらに電気代節減が出来ます。これが大きなメリットと感じます!
導入後の効果については、以下記事で記載させていただきました。是非ご覧ください。
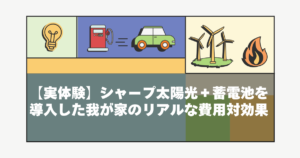
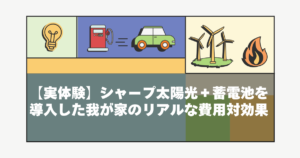
メリット2:災害時の電源確保
蓄電池は災害時の非常用電源として非常に有効です。
地震や台風などで停電が発生した際に、蓄電池に蓄えた電力を使うことで、冷蔵庫や照明、通信機器などを使用し続けることができます。
蓄電池が太陽光で発電した電力を保存しておくため、災害時でも一定期間、家電を使い続けることができるからです。特に、停電が長期間続く場合でも、蓄電池があれば電力の供給が続くため、安心感が得られます。



昨年の夏の台風で、停電に備えて、蓄電池を満充電にしました。結局使用しませんでしたが、安心感を得る事が出来、大きなメリットと感じました!
メリット3:太陽光発電システムの効率最大化
蓄電池は太陽光発電システムの効率を最大化します。
太陽光パネルだけでは、発電した電力をすべて使い切れず、余った電力を売電することが一般的ですが、蓄電池を設置することで、発電した電力を無駄なく自家消費することができます。
蓄電池が発電した電力を蓄え、必要なときに使用できるため、昼間に発電して余った電力を売電することなく、自家使用できるからです。これにより、売電価格の変動に左右されることなく、安定した電力使用が可能になります。
蓄電池導入にかかるコストとその回収期間は?


蓄電池の設置にはコストがかかりますが、その後の電気代削減効果を考慮すると、導入を検討する価値があります。
ここでは、蓄電池の導入にかかる費用と、どれくらいでコストを回収できるかについて詳しく解説します。
- 蓄電池の導入コスト
- コスト回収期間はどのくらいか?
- 助成金や補助金を活用する方法
- 蓄電池の寿命:一般的に10〜15年
蓄電池の導入コスト
蓄電池の導入には初期費用がかかります。一般的に、蓄電池の設置にかかる費用は、1kWhあたり約15〜25万円程度と言われています。システムの容量やメーカー、設置場所によって価格は異なりますが、家庭用の蓄電池であれば、概ね60万円〜200万円ほどの費用がかかることが多いです。
蓄電池の技術が進化し、容量や性能が向上しているため、その分初期投資が高くなるからです。また、設置作業や電気配線工事が必要で、その費用も全体のコストに含まれるため、一定の費用がかかります。
コスト回収期間はどのくらいか?
蓄電池のコスト回収期間はおおよそ10〜20年程度と思います。
結構かかりますね。



我が家の場合も、蓄電池購入価格が約180万円程ですので、約15年くらいは回収に期間がかかります。ですので、コスト回収も出来たら良いくらいにして、その他、災害対策等のメリットにフォーカスする事をお勧めします!!
蓄電池を導入することで、昼間の余剰電力を夜間に自家消費でき、電力会社から購入する電力を減らすことができるため、毎月の電気代が削減されます。平均的な家庭であれば、年間で約10万円〜15万円の電気代削減が期待できます。
助成金や補助金を活用する方法
蓄電池の設置費用を抑えるためには、政府や自治体の助成金や補助金を活用することが有効です。
多くの自治体では、蓄電池導入のための補助金や助成金を提供しており、これを利用することで、初期投資を大幅に削減できます。
補助金を活用することで、コスト回収期間も短縮され、さらに導入のハードルが低くなります。
蓄電池の寿命:一般的に10〜15年
蓄電池の寿命はおおよそ10〜15年程度とされています。これは、蓄電池の種類や使用環境、メンテナンス状況により異なりますが、一般的にこの期間が目安となります。
蓄電池には使用回数や充放電サイクルに制限があり、長期間の使用や頻繁な充放電を行うと、徐々にその性能が低下していくからです。使用する電力の量や充電の頻度が高いほど、寿命が短くなる可能性があります。
リチウムイオン蓄電池は約6000回〜12000回の充放電サイクルを持っているとされています。これを一般家庭の使用頻度に換算すると、15年程度で寿命を迎えることが多いとされています。
ミライでんち
【FAQ】よくある質問とその回答
- 蓄電池はどのくらいの寿命がありますか?
-
蓄電池の寿命はおおよそ10〜15年程度が目安です。しかし、使用状況やメンテナンスの状況によって、寿命は変動します。例えば、充放電の頻度や蓄電池の設置場所の温度管理が影響を与えるため、適切な運用が求められます。
- 蓄電池を設置する場所に特別な条件はありますか?
-
蓄電池を設置する場所には、通気性の良い場所を選ぶことが重要です。高温多湿の場所や直射日光が当たる場所は避け、できる限り温度が安定している場所に設置することをおすすめします。
- 蓄電池を設置することで電気代はどれくらい安くなりますか?
-
蓄電池を設置することで、日中に太陽光パネルで発電した電力を自家消費できるため、電気代が大幅に削減できます。特に電力消費が多い家庭では、年間で数万円の節約効果が期待できることがあります。
- 蓄電池は設置後、どれくらいで元が取れるのでしょうか?
-
蓄電池の導入で得られる電気代の削減効果によって元を取る期間は家庭ごとに異なりますが、一般的には10〜20年程度で元が取れると言われています。これには、設置費用、電力使用量、電力料金の変動などが影響します。
- 災害時にも蓄電池は使えるのでしょうか?
-
蓄電池は、停電時に備えて電力を供給することができます。災害時に電力供給が途絶えると、蓄電池があれば非常に役立ちます。ただし、蓄電池が全ての電力を賄えるわけではないので、使用する電力を適切に管理することが大切です。
まとめ
- 蓄電池の寿命は10〜15年が目安で、使用状況やメンテナンスによって変動します。
- 蓄電池の導入費用は60万円〜200万円程度で、長期的なコスト削減効果を考慮することが重要です。
- 蓄電池の設置場所は通気性が良く、温度が安定している場所を選びましょう。
- 蓄電池を選ぶ際は容量、メーカーの信頼性、保証内容、コストパフォーマンスを重視することが大切です。
- 蓄電池は停電時の電源確保に役立ち、災害対策としても有効ですが、使用電力の管理が必要です。
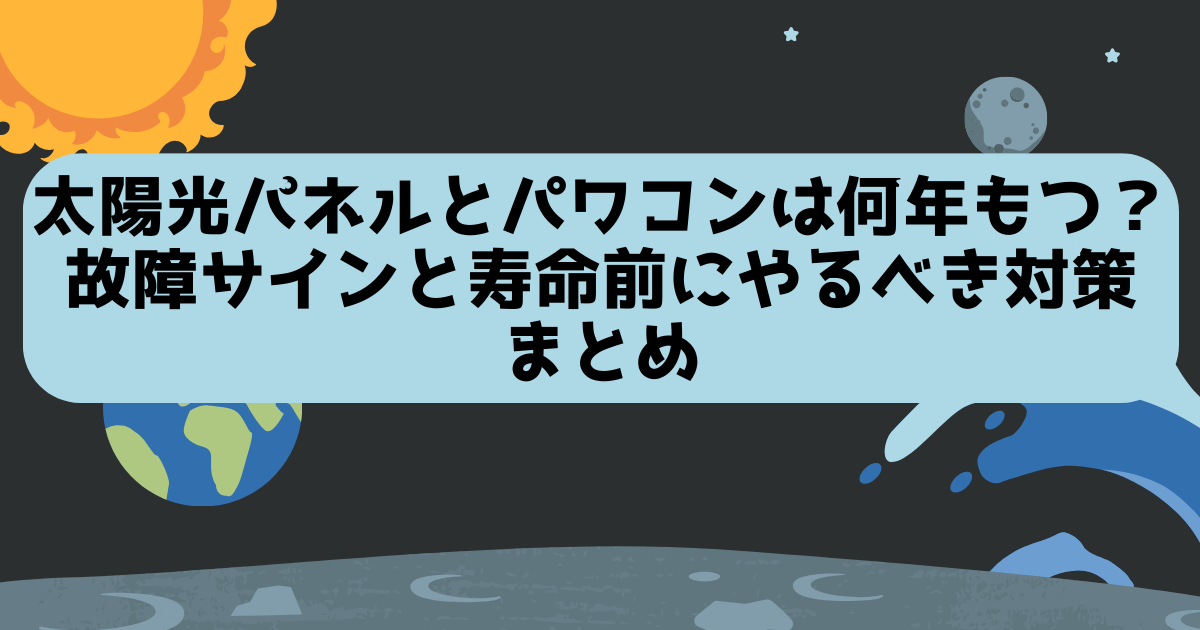
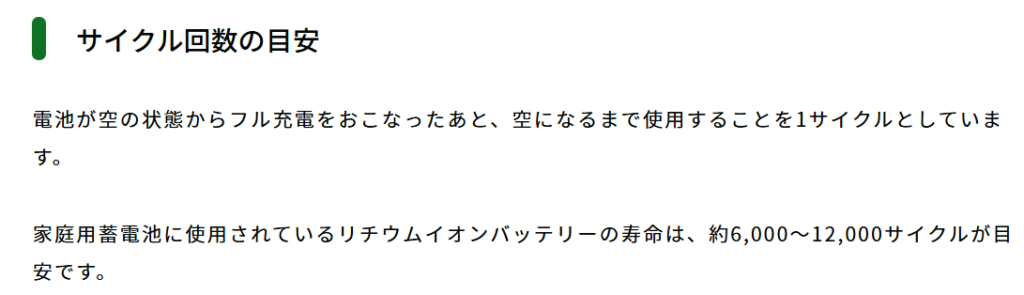
コメント